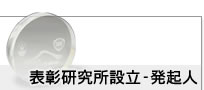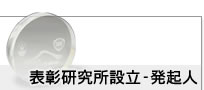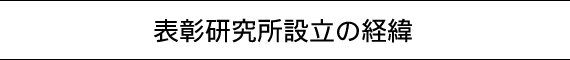
文:田村信夫
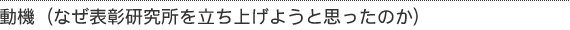
この度、日本表彰研究所を立ち上げることになりました。私田村信夫は父親の代から表彰楯の製造や表彰用品の販売を手がけています。
私は長年表彰に携わる仕事をしながら、そもそも「表彰」は何を目的に行われているのか、表彰する人は表彰によってどのような効果、影響を期待しているのかということを
考え続けてきました。表彰を実施する組織や機会によって、その答えは様々だと思いますが、表彰される相手のモチベーションを上げたり、雰囲気を良くすることが、
「表彰」の重要な目的であることも分かってきました。
しかし、その目的が実現しているのか、思ったような成果を上げられているのかということについては、そこまで調査研究されている例はきわめて少ないということも分かってきました。そこで、そういったことを本腰を入れて調査研究してみようと思ったのが、日本表彰研究所を立ち上げようと思ったきっかけです。
そうした時に、同志社大学教授の太田肇先生と出会いました。太田先生は、人を認めることがモチベーションアップにつながり、人々を幸福にし、組織も活性化するということを、長年にわたって研究されてこられた方です。私も表彰のベースには、人を認めるということがなければならないと考えていましたので、先生の研究にたいへん興味を持ち、表彰研究所の所長になっていただきたいとお願いしました。太田先生との出会いがなければ、日本表彰研究所の設立はなかったと思います。
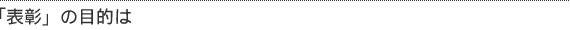
「表彰」とは、優れた功績を公に明らかにし、表彰された人の意識を高揚させると共に、組織を活性化したり、業績を向上させようという
意図があります。そう考えると、表彰を行うことによって表彰された人の意識が高揚したかどうか、組織が活性化したり、業績が向上したかどうかが、
表彰の目的が達成されたかどうかを判別する基準になります。表彰を単に慣例的に行うのではなく、本来の目的が達成できているかどうかを確かめることも重要だと思います。
また、仮に表彰された人の意識が高揚したとしても、周囲の人の意識が低下してしまっては、組織全体の向上にはつながりません。表彰は表彰する人と
表彰された人だけでなく、組織全体のことを考えて実行し、効果検証する必要があります。
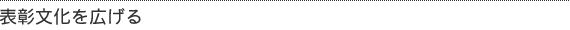
「表彰」とは善行や功労、成果などを公に明らかにすることですが、同時に相手を認めるということでもあります。
一般的に「表彰」というと、優れた功績に対してだけ行われることが多いように感じますが、もっと気軽な表彰、カジュアルな表彰、パーソナルな表彰があっても
いいのではないでしょうか。何故なら、表彰は、相手を認めているということを、積極的に伝える行為でだからです。
表彰文化を広げるということは、お互いがお互いを認め合う社会を作り上げることなのです。
表彰文化を広げるためには、社会の色々な組織、分野、地域などで表彰する機会を増やさなければなりません。しかし、従来の表彰の
イメージしかなければ、気軽な表彰、カジュアルな表彰、パーソナルな表彰は、なかなか増えていかないでしょう。お互いがお互いを認め合う社会を作り上げる
ためには、表彰の効果効能を理解する人を増やし、表彰の機会を増やす必要があります。
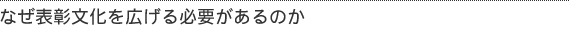
現代社会は、物質的には非常に恵まれていますが、反面、孤独感や孤立感を感じている人が増えているように感じます。様々な社会問題も
孤独感や孤立感に起因しているものも少なくないと思われます。人はお金や物さえあれば幸福になれる訳ではありません。
人から認められているという安心感や満足感がなければ、絶対に幸福にはなれません。幸福な世の中を作るためには、認められているという安心感や満足感を
感じる機会を増やす必要があります。
以上のような理由から、表彰の機会を増やすことは、社会的にもたいへん意義あることだと思います。世の中から認められた人は安心感を持ち、
やる気が高まり、活性化します。表彰文化を広げることは、世の中に安心と活気を生み出します。表彰文化を世の中に広げることの趣旨を理解していただき、
一人でも多くの方に表彰文化を広げる活動に参加していただけることを熱望しています。
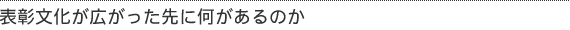
表彰する、表彰される機会が増えていくということは、お互いがお互いを認め合う社会につながっていきます。世の中には、歴史、宗教、文化、
生活慣習などが違う、多様な民族が共存しています。しかし、そうした違いを乗り越え、お互いがお互いを認め合えば、いざこざや紛争、無意味な争いもなくなり、
平和で幸福な社会の実現に向けて大きく前進します。表彰文化を広げることは世の中の平和と幸福につながると信じています。
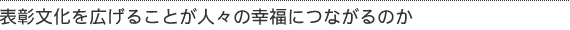
表彰文化を広げる目的には、お互いがお互いを認め合う機会を増やし、安心で活気ある社会を作りたいということがあります。また、表彰の基準を明確にすることはそれぞれの価値観を明確にすることであり、多様な価値観の存在を認識することにもつながります。
人間は一人では生きていけません。人と人のつながり無くして社会生活を営むことは不可能です。しかし、組織に属しているからといって、また組織の一員であるからといって、人と人のつながりができているのかというと、必ずしもそうは言えません。人と人のつながりができるためには、相互理解と相互認識が必要です。人は人から認められているという安心感をもてない限り、人とのつながりを感じることはできません。
逆に、人は人から理解されている、認められていると感じたときに安心感が生まれ、生きる自信が生まれます。平穏な心を持ち、自信を持って行動している人ほど幸せな人はいないのではないでしょうか。幸福感はものやお金では得られません。心の平穏と自信こそが幸せになるための必要条件なのです。
世の中には様々な考え方や主義主張があります。また多くの宗教や人種、地域、歴史の違いがあります。それらは多種多様な価値観を生み出し、世の中には人間の数だけの価値観があるといっても過言ではないと思います。しかし、価値観が違うからと言って、相手を認めないということでは、世の中で生きていけません。健全な社会生活を営むためには、違う価値観の人を受け入れることが必要条件なのです。
そのためには、まず自分の価値観を明確にしなければなりません。組織であればその組織の価値観を明確にしなければなりません。そして、お互いがお互いの価値観を理解し、自分以外の価値観を受け入れる器の大きさを持たなければなりません。
地球上の全ての人がこのように努力していけば、世の中から無益な争いや紛争は限りなく少なくなっていくことでしょう。その先には、幸福な世の中が待っていると信じています。
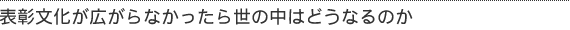
表彰文化が広がらなければ、表彰を通じてお互いがお互いを認め合うという機会が増えない、あるいは少なくなるということを意味しています。お互いがお互いを認め合うということは、必ずしも表彰という行為を通じてしか行えないという訳ではありません。しかし、機会が減ることは確かです。
機会が減る以上に心配なのは、お互いがお互いを認め合うということの大切さを、世の中の人がどれだけ理解しているのかということです。世の中の全ての人が、お互いがお互いを認め合うということさえ理解してもらっていれば、別に表彰という手段をとらなくても別の手段で目的を達成してもらえばいいと思います。
気をつけないといけないのは、いくら自分が他の人を認めていても、それが相手に伝わらなければ、お互いを認めることによる効果が得られないのです。お互いがお互いを認め合うということも、手段であり目的ではありません。目的は安心感を持つことであり自信を持つことなのです。人から認めてもらっているということが分かれば安心し、自信が持てるのですが、認めてもらっていることが分からないために安心できなかったり、自信が持てなかったりする人はたくさんいます。
表彰文化が広がらない原因が、お互いがお互いを認め合うことの大切さを理解していない、あるいは、理解していても相手を認めていることを伝えることの大切さを認識していないというところにあれば、たいへん心配なことです。
では、お互いがお互いを認め合わない社会はどんな社会になるのでしょうか。それは常に不安を抱え、生きる自信が持てない人が大量に発生する社会を意味します。常に不安を抱え、生きる自信が持てない人がたくさんいる社会は健全な社会なのでしょうか。安定した社会なのでしょうか。不安や自信のなさは自殺や犯罪の多発の引き金にもなります。決して健全な社会ではありません。未来を明るく幸福な社会にするためにも、お互いがお互いを認め合う機会を増やさなければなりません。
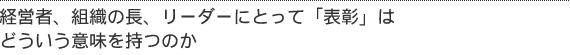
人の上に立つものは、部下の能力を引き出すということや、正しい方向に導くことをその大切な役割としてもっています。また、部下に対して敬意と感謝の気持ちを常に持たなければなりません。「表彰」はそれを実現する、あるいはそういう気持ちを持っていることを表すよい機会になります。
全ての部下は上司に認めてもらいたいという気持ちを持っています。また明確にそういった願望を持っていなくても、潜在的にそういう欲求をもっているはずです。表彰は部下を認めていることを積極的に伝えるよい機会になります。
また、表彰するためにはその基準を決めなければなりません。その基準とは会社の理念や方針、経営者の価値観、その時々の目標に準じたものになるはずです。表彰の基準を明確にし、その基準に沿って表彰を行うことは、経営理念、方針、経営者の価値観、目標を全スタッフに伝えることにつながるのです。
表彰の目的に、スタッフのやる気を高め、その組織の業績に寄与して欲しいということがありますが、そういった組織に対しての期待を求めるだけでなく、純粋にスタッフに対して感謝の気持ちを伝えることも大切なことだと思います。組織は、その組織を構成する人がいて初めて成り立つのです。自分がその組織の長でいられるのも、その組織を構成するスタッフがいるからこそです。表彰によって部下の能力ややる気を引き出すだけでなく、部下に敬意と感謝の気持ちを伝えるということを同時に行わなければなりません。
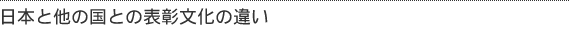
日本人は農耕民族であり、組織の調和を大切にするという伝統文化があります。一人のヒーローよりも、みんなが力を合わせて一定の成果を出すことを重んじます。従って、あまり派手な表彰式がそれほど多くありませんし、自分だけが表彰されることで、かえって気を遣う人もいます。日本の社会には出る杭を打つという風潮があるのを敏感に感じ取っているのかもしれません。
アメリカにはヒーローを賞賛するという社会風土があります。それが表彰の機会の多さにつながっているのかもしれません。また、表彰する側にとっても、スタッフをどんどん表彰してモチベーションを上げ、自分や自分の組織の業績を上げることに寄与させようという意図を感じます。
しかし、アメリカと同じ手法をまねしても、日本の社会では必ずしもうまくいくとは限りません。それは、アメリカと日本では社会が構成されてきた歴史的経緯がまるで違うからです。日本の社会に合った表彰の仕方を学ぶ必要があります。
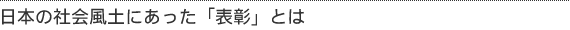
日本の社会風土にあった表彰とはどういうものでしょうか。日本人にもヒーローになりたい人はいるでしょうけれど、アメリカ人に比べるとそれほど多くないと思われます。また、ヒーローになりたいと思っている人でも、大勢の前で賞賛されると気恥ずかしさを感じてしまうことも少なくありません。それは、日本人が古くから調和を重んじ特定の人だけが突出することを戒めてきたという歴史があるからでしょう。
日本の社会風土にあった表彰は、ヒーローを称えるというよりも、その人を認めるという意味合いを強くしたものではないでしょうか。表彰の基準を明確にし、その人が本当にその基準を満たすことに努力し、成果を出したということを、公式に認めるということであれば、周囲の人も納得するし、本人も気恥ずかしくないはずです。
|