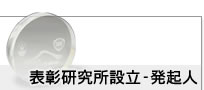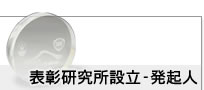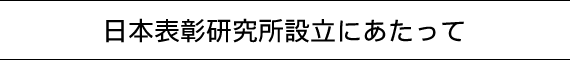

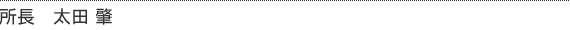

ヨーロッパを旅すると、町のいたるところで偉人や英雄の銅像を目にする。そこには、学術や文化、産業などの発展に貢献した人を讃えようという市民の意思がうかがえる。アメリカの企業に足を踏み入れると、オフィスのデスクには表彰でもらった盾や置物がたくさん飾られている。表彰用の小物を作る会社が日本の10倍もあるそうだ。サクセス・ストーリーが好きな国だけあって、ヒーローや成功者には周囲が惜しみない拍手を送る。
それに対してわが国では、「出る杭は打たれる」「高木は風に折らる」といわれるように、突出した能力や業績、ユニークな個性を認めたがらない。「バッシング」や「KY」といった言葉が流行するのをみても、そうした傾向はむしろ強まっているように感じる。私は優れた能力・業績・個性を称讃することを<表の承認>、分(ぶ)や序列をわきまえ、出過ぎないことをよしとするのを<裏の承認>と呼んでいるが、日本の社会や組織は<裏の承認>にたいへん厳しい。「裏承認の国、ニッポン」である。
各種意識調査にもそうした日本人、日本社会の特殊性は顕著に表れている。人生の目標として「高い社会的地位や名誉を得ること」と答えた中高生は、アメリカで41%、フランスで18%いるのに対し、日本ではわずか2%にすぎない。高い志や野心を抱けない若者の姿が浮かび上がってくる。そして社会人を対象にした調査では、日本人の仕事に対する熱意や仕事に対する満足度が、国際的にみてきわめて低い水準にあることがわかってきた。それは、他の主要国に比べて低い労働生産性、世界に占める日本のGDPの比率低下、そして国際社会における存在感の希薄化と無関係ではなかろう。このままだと日本人、日本社会の活力はますます低下し、沈滞し続けることが危惧される。
それを食い止め、活力をよみがえらせるには、<表の承認>の機会と文化を組織の中、そして社会全体に広げていくことが大切である。個人に夢と希望を与え、組織や社会はそれを支援していかなければならない。そのための有力な手段の一つが表彰である。とりわけ日本的な社会風土の特殊性を考えた場合、このような「仕掛け」づくりが必要であろう。
日本社会の特徴や集団の人間関係、日本人のメンタリティなどに照らして、どのような表彰制度が有効なのか、どういったプロセスで導入していけばよいのか。それを研究し、成果を普及・啓発することは社会的にきわめて意義のある使命だと考えられる。さらに、さまざまな人々や団体を巻き込んで国民運動へと発展させることができるなら、日本経済、日本社会の浮揚にも貢献できるであろう。
皆様方のあたたかいご理解とご支援を賜りたい。
| 太田 肇 |
|
1954年生まれ。同志社大学政策学部教授。経済学博士。『承認欲求』、『お金より名誉のモチベーション論』(ともに東洋経済新報社)、『選別主義を超えて』、『個人尊重の組織論』(ともに中公新書)、『仕事人の時代』(新潮社)など著書多数。組織学会賞、経営科学文献賞、中小企業研究奨励賞本賞などを受賞。
|
|